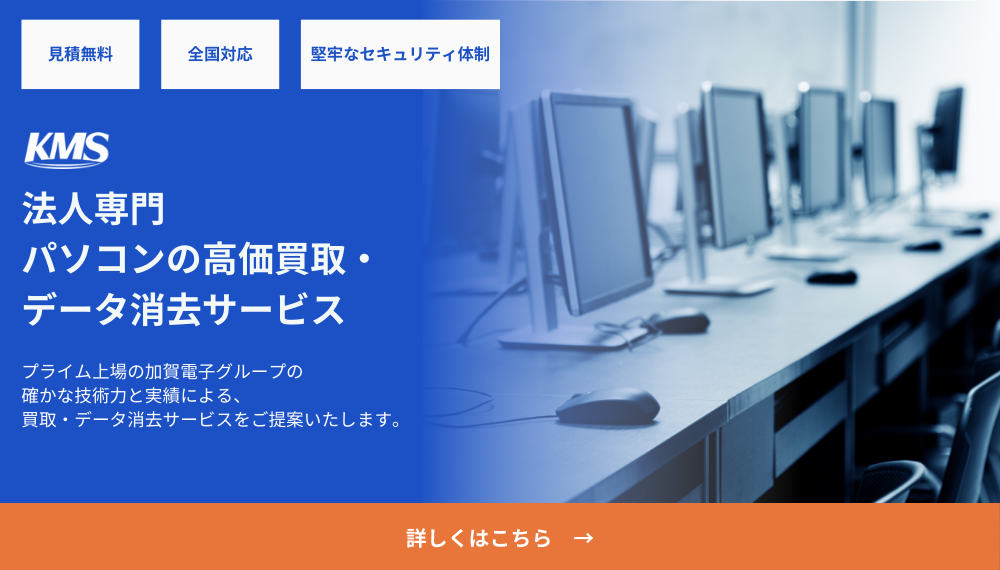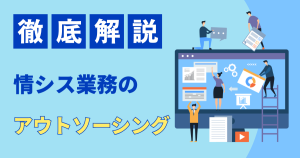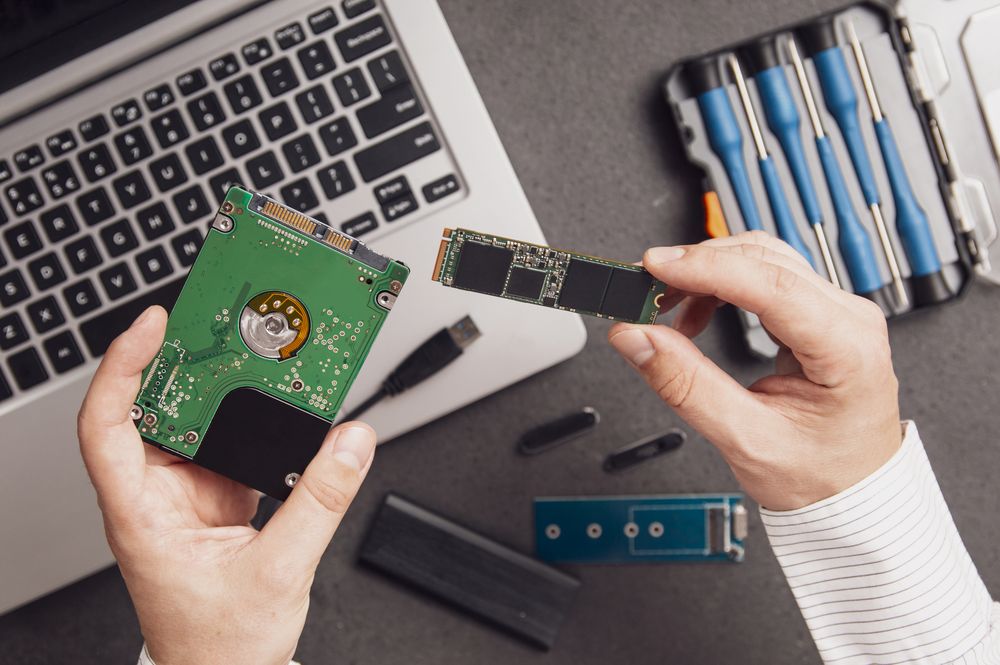サーバーとは?パソコンとの違いや種類・用途について解説

サーバーは会社が事業を行ううえで、必須のITインフラであり重要な存在です。
しかし、「PCとの違い」や「クラウドとオンプレ、どちらを選ぶべき?」などの疑問を抱いている人も多いでしょう。
そこで今回の記事では、サーバーの基本的な仕組みや種類、PCとの違いを分かりやすくまとめました。
さらに、オンプレ・クラウドなどの利用形態や運用時の注意点まで解説していますので、ぜひ最後まで読んでください。
不要になったパソコン/スマホの処分にお困りなら
【法人専門】高額買取・データ消去サービス
サーバーとは?
まずはサーバーの概要を解説します。
サーバーとは?
サーバーとは、サービスの提供やデータの保管を担うコンピューターのことです。
クライアントPCやスマホなどからの要求(リクエスト)に応じて、必要な処理や情報を返します。
たとえば、X(旧Twitter)ではユーザーが投稿すると、その内容がサーバーに送信されて保存されます。
また、ほかの人の投稿を閲覧する際にはサーバーにリクエストを送り、サーバーがデータを返す仕組みです。
つまりサーバーは、ユーザーからのリクエストに応じて、データの保存や処理・提供を行うコンピューターです。
サーバーの種類
サーバーには役割に応じてさまざまな種類があります。
たとえばWebサーバーは、クライアントから「このサイトを見たい」というリクエストを受け、Webサイトの情報や画像を返す役割を行います。
代表的なサーバーの種類は以下のとおりです。
| 主な役割・特徴 | |
|---|---|
| Webサーバー | Webサイトやアプリのページを提供する |
| DB(データベース)サーバー | データを保存・検索・更新する |
| ファイルサーバー | 文書・画像・動画を共有・管理する |
| メールサーバー | メールの送受信・保管を行う |
このほかにもDNSサーバーやプロキシサーバーなど、さまざまな種類のサーバーが存在します。
企業にサーバーが必要な理由
企業でサーバーを利用する最大のメリットは、データを一元管理できることです。
顧客情報や財務記録、従業員データなどの重要情報をサーバーに集約すれば、複数の部門や社員が同じデータを参照でき、整合性を保てます。
もし各PCに個別でデータを保存していた場合、更新のタイミングがバラバラになり、正しい情報をもとに業務が行えません。
さらに、サーバーを活用することでバックアップやアクセス制御を行えるため、情報漏洩やデータ消失などのリスク対策にもつながります。
サーバーとPCの違いを分かりやすく比較
続いてサーバーとクライアントPCの違いを解説します。
1.用途の違い
| サーバー | クライアントPC | |
|---|---|---|
| 使用目的 | 複数ユーザーに対する ・サービス提供 ・データ共有 | 個人ユーザーの ・サービス利用 ・パソコン内のソフト利用 |
| 具体例 | ・Webサービスを提供するWebサーバー ・ファイル共有を行うファイルサーバー | ・Webの閲覧 ・インストールされたExcelの利用 |
サーバーはサービスを提供するために利用されます。
たとえば、社内のファイルを一元管理するファイルサーバーや、Webサイトを配信するWebサーバーが代表的です。
一方でクライアントPCは、ユーザーがパソコンを通じてサービスを利用するための端末です。
サーバーから送られた情報を受け取り、画面上に表示したり操作したりする目的で使います。
このように、サーバーは「サービス提供」、クライアントPCは「サービス利用」する目的として、役割が分かれています。
2.ハードウェアの違い
| サーバー | クライアントPC | |
|---|---|---|
| 耐久性・ パフォーマンス | ・高品質な部品を採用 ・電源の冗長化(UPSや二重化電源) ・強力な冷却システム ・24時間365日稼働が前提 | ・標準的な部品 ・電源の冗長化なし ・一般的な冷却システム ・業務時間内の使用が前提 |
| CPU | サーバー専用CPU(Intel Xeon など) 複数ソケット対応(2基~4基搭載可能) マルチスレッドで高負荷に強い | 一般的なCPU(Intel Core、AMD Ryzen など) |
| メモリ | 大容量(一般的に数十~数百GB) ECCメモリでエラー耐性が高い | 標準的(8~16GB程度) |
| ストレージ | 大容量かつ高速なRAID構成(数TB~数十TB) 冗長化で故障に備える | 一般的なストレージ(256GB~1TB程度のSSD/HDD) |
サーバーは「壊れない」「止まらない」「処理落ちしない」ことを前提に設計されています。
そのため電源やストレージは冗長化され、部品も長時間稼働に耐えられる高品質なものが使われます。
スペック面でも、同時に複数ユーザーのリクエストに応えることを前提しています。
CPUは Xeon などのサーバー専用モデルを採用し、マルチソケット対応で処理能力を拡張できます。
さらに、ECCメモリによってメモリエラーを自動修正できるため、安定した使用ができます。
一方、クライアントPCは個人利用を前提に設計されており、操作性やコストパフォーマンスを重視します。
3.ソフトウェアの違い
| サーバー | クライアントPC | |
|---|---|---|
| OS | Windows Server、Linux など | Windows 10/11、macOS など |
| よく使う アプリケーション | 他の端末からアクセスされることを前提としたアプリケーション (例:業務システム、データベース、ファイル共有、ドメイン管理など) | 日常業務向けのアプリケーション (例:Word、Excel、Chrome など) |
| 特徴 | 複数ユーザーによる同時アクセスや高負荷処理に最適化し、安定性・機能性を重視。 | 操作性や利便性を重視 |
サーバーには Windows Server や Linux などのサーバー専用OSがインストールされます。
これらはサービス提供や複数ユーザーの同時アクセスを想定して設計されており、安定稼働や長時間の連続稼働が求められます。
加えて、ファイル共有・データベース・認証管理など、管理者向けの機能を備えています。
一方、クライアントPCには Windows 10/11 や macOS が一般的で、1ユーザーが使うことを前提にしたOSです。
サーバーに比べ操作性や利便性を重視し作られています。
4.コストの違い
| サーバー | クライアントPC | |
|---|---|---|
| 新品価格 | 30~200万円 | 5~20万円 |
一般的にサーバーは30万円前後から販売されており、性能や用途によっては200万円を超えるケースもあります。
これはサーバーが高性能なハードウェアを搭載しているうえに、OSライセンスや長期のハードウェア保証などが含まれるためです。
さらにサーバーは導入費だけでなく、以下のような運用コストも発生します。
・サーバールームの冷却に伴う光熱費
・サーバーを管理する担当者の人件費
・ベンダーによる保守費用
このように、サーバーはクライアントPCに比べて「導入費」と「運用費」の両方でコストがかかります。
サーバーの利用形態

サーバーには以下の利用形態があります。
・物理サーバー
・仮想サーバー
・オンプレサーバー
・クラウドサーバー
それぞれの特徴やメリット・デメリットを押さえましょう。
物理サーバーと仮想サーバー
| 物理サーバー | 仮想サーバー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 1台のマシンに1つのサーバー | 1台のマシンに複数のサーバーを構築可能 |
| メリット | ・専用利用により性能が安定 ・CPU・メモリ・ストレージを占有できる | ・複数サーバーを作れるのでコスパが良い ・サーバー追加が容易で柔軟に拡張できる |
| デメリット | ・複数のサーバー環境を作れない ・小規模システムではリソースを余らせる ・サーバー追加は機器購入が必須 | ・性能が落ちやすい(他の仮想サーバーの影響を受ける) ・仮想化ソフトの運用知識が必要 |
| おすすめ 用途 | ・ユーザー数が多く、高度な処理が必要な基幹システム | ・ユーザー数が少なく、複雑な処理を必要としないシステム ・セカンダリ(予備)システム |
物理サーバーとは
物理的な1台のマシンをそのままサーバーとして利用する方式です。
CPUやメモリ、ストレージを占有できるため性能が安定し、大規模な業務システムや高負荷処理に向いています。
ただし、小規模なシステムではリソースを使い切れず、コストパフォーマンスが悪くなりがちです。
仮想サーバーとは
1台の物理サーバーの中に、仮想化ソフト(VMware、Hyper-V、KVMなど)を使って複数の仮想サーバーを作る方式です。
リソースを効率的に分割でき、柔軟な拡張も可能なため、コストを抑えて運用できます。
ただし、物理リソースを複数で共有するため性能低下が起こりやすく、基幹系システムのように「絶対に止められない業務」には不向きです。
オンプレサーバーとクラウドサーバー
| オンプレサーバー | クラウドサーバー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 自社にサーバー機器を設置 | 事業者のデータセンターを利用 |
| メリット | ・自由なカスタマイズが可能 ・トータルコストが安くなる傾向 | ・導入がスピーディー ・初期費用が不要 ・必要に応じたリソース調整が可能(従量課金) |
| デメリット | ・サーバー調達や構築で初期費用が高額 ・導入までに時間がかかる ・運用は自社担当者の負担が大きい | ・オンプレに比べるとカスタマイズに制限がある ・長期利用ではコストが高くなる傾向 |
| おすすめ用途 | ・機密情報を多く扱う業務 ・特殊なカスタマイズが必要なシステム | ・短期間を想定したシステム ・アクセス数が変動するWebサービス ・初期投資を抑えたい中小企業 |
オンプレサーバーとは
自社内にサーバー機器を設置・運用する形態です。
自社環境に合わせて細かいカスタマイズができます。
ただし、初期費用が高く、導入に時間がかかるほか、運用担当者の負担も大きくなります。
クラウドサーバーとは
クラウド事業者が提供するサーバーを、インターネット経由で利用する形態です。
すでに機器が用意されているため、申込後すぐに利用を開始でき、必要な分だけ従量課金で支払う仕組みが一般的です。
他社が提供するサービスであり、自由なカスタマイズは制限され、長期利用では費用がかさむこともあります。
サーバー運用は注意が必要!気を付けるポイントについて
サーバーは通常のPCに比べて高い負荷の処理を行います。
そのため障害が起きると影響範囲が大きく、サーバーを利用するすべてのユーザーの業務が止まってしまう可能性があります。
安定した運用のためには、次のポイントに注意する必要があります。
安定性・耐久性の確保
サーバーは多くの場合24時間365日の稼働が前提です。必要に応じて専用のサーバールームを設け、冷却設備やUPSの導入・二重化電源の構成を行いましょう。
セキュリティ対策
外部からの不正アクセスやウイルス感染を防ぐため、ファイアウォールや侵入検知システムを導入し、定期的なセキュリティ更新を行いましょう。
バックアップ体制
データ消失に備えて、定期的なバックアップを取得し、災害時には別拠点から復旧できる仕組みを整えましょう。
サーバーは「止まらない・壊れない・安全である」ことが求められるため、導入後の運用管理こそが最大のポイントとなります。
サーバーは自社に合ったものを選びましょう
今回の記事では、サーバーの種類やクライアントPCとの違いを解説しました。サーバーは、データの保存や処理を担い、業務に欠かせない存在です。サーバーの利用形態としては、「物理・仮想」や「オンプレ・クラウド」などがあります。
それぞれの特徴を押えたうえで、自社サーバー運用の参考にしましょう。
IT資産の管理をご担当している方は、サーバー以外にも通常のクライアントPCの導入や廃棄業務にも携わっていらっしゃると思います。
加賀マイクロソリューションでは、法人向けのパソコン買取・データ消去サービスを提供しています。
累計100万台以上の実績があり、安全なデータ消去・高額買取のご提案が可能です。PCやスマートフォンの処分にお困りの際には、是非お気軽にお問い合わせください。