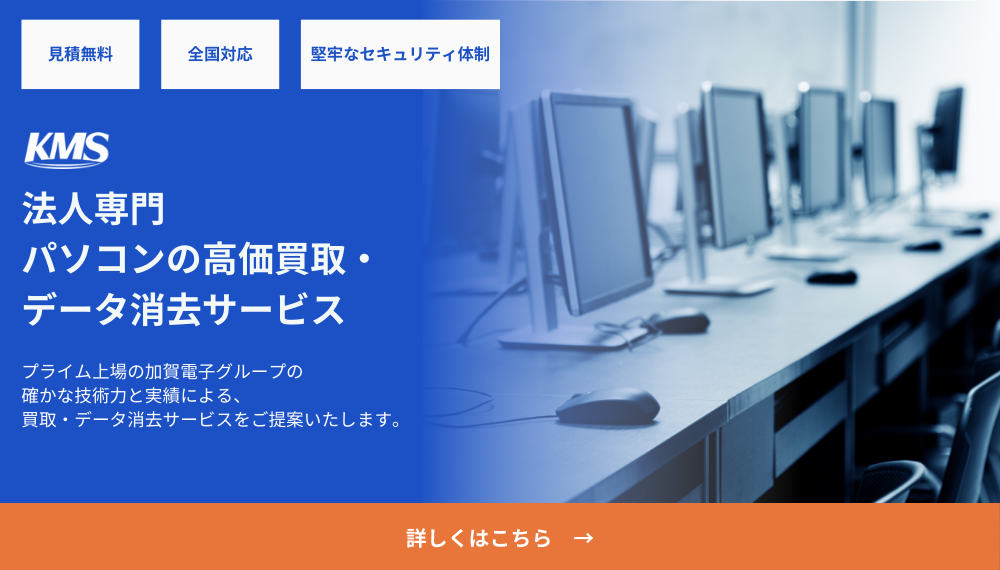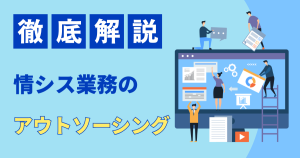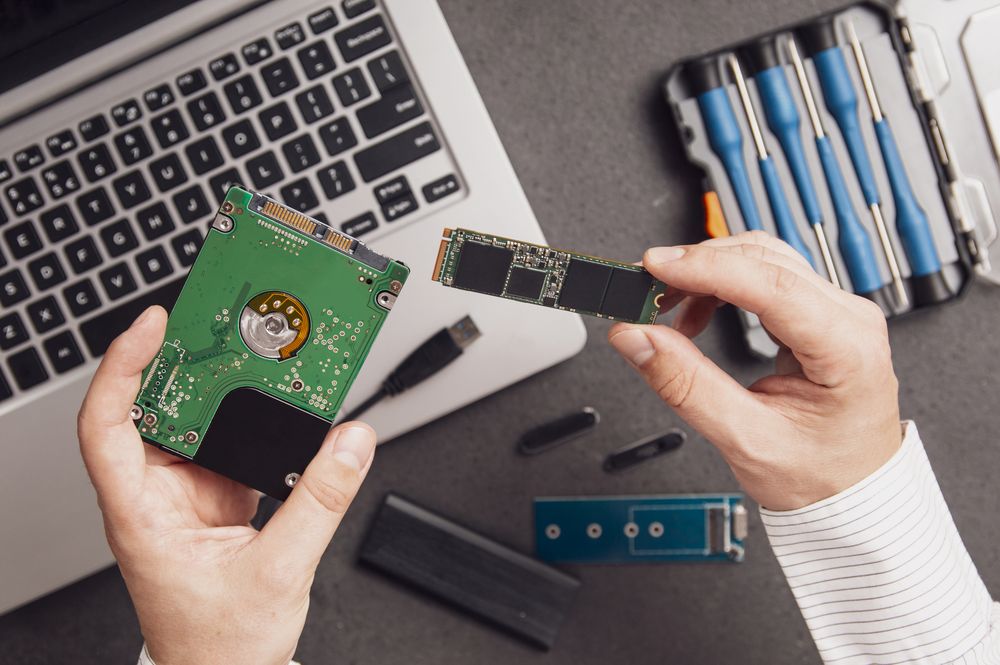情シス必見!企業がするべきマルウェア対策と感染時のリスクを徹底解説

業務システムの停止、機密情報の流出、そして多額の身代金要求。これらによる被害は、もはや一部の大企業に限った話ではなく、中小企業を含むあらゆる組織が直面する現実です。
このようなサイバー攻撃の巧妙化・高度化が進む中で、企業の情報資産を脅かす最大のリスクの一つが「マルウェア」です。
マルウェアは、ウイルスやランサムウェア、トロイの木馬といった多様な形で企業ネットワークに侵入し、セキュリティ対策の隙を突いて深刻な被害を引き起こします。
本ページでは、マルウェアの基本的な分類から感染経路、そして実効性の高い対策までを体系的に解説し、IT管理者が取るべき現実的な防御策を詳しく解説します。
不要になったパソコン/スマホの処分にお困りなら
【法人専門】高額買取・データ消去サービス
マルウェアとは
マルウェア(Malware)とは、「malicious software(悪意のあるソフトウェア)」の略語で、コンピュータやネットワークに損害を与えたり、不正な操作を行ったり、情報を盗んだりすることを目的に作られたソフトウェアの総称です。
代表的なマルウェアの種類
マルウェアは、大きく分けて11種類あります。
| 種類 | 実行方式 | 自己増殖 | 特徴・説明 |
|---|---|---|---|
| ウイルス型 | 他のファイルに寄生して実行 | 可能 | 単体では実行できず、他の実行ファイルに付着して広がる。 |
| ワーム型 | 単体で実行可能 | 可能 | ネットワークを通じて自己増殖。拡散力が強い。 |
| トロイの木馬型 | 単体で実行可能 | 不可 | 有益なソフトを装うが、裏で悪意ある動作を行う。 |
| ランサムウェア | 単体で実行可能 | 場合による | ファイルを暗号化し、復号に金銭を要求。 企業が標的になることが多い。 |
| スパイウェア | 単体で実行可能 | 不可 | ユーザーに気づかれずに情報を盗む。気づきにくいのが特徴。 |
| アドウェア | 単体で実行可能 | 不可 | 強制的に広告を表示。 合法なものもあるが、悪質なものはマルウェア扱い。 |
| バックドア | 単体で実行可能 | 不可 | 攻撃者が外部から侵入する「裏口」を作る。目立たない。 |
| ボット | 単体または複合型 | 可能 | 感染後に外部からの指令で動作。 多数のボットで構成される「ボットネット」が攻撃に使われる。 |
| スケアウェア | 単体で実行可能 | 不可 | 偽の警告を表示し、不安を煽って金銭や個人情報を取得。 |
| キーロガー | 単体で実行可能 | 不可 | キーボード入力を記録し、パスワードなどを盗む。 |
| ファイルレスマルウェア | メモリ上で動作 | 不可 | 実体のファイルを持たず、検知が困難。 メモリやOSの機能を悪用。 |
単体の分類だけではなく、複合的に要素を持ったマルウェアも存在します。
企業PCへのマルウェアの感染経路
企業内のシステムデバイスに、不正にマルウェアが侵入することを「マルウェア感染」と言います。
マルウェア感染の経路として挙げられるものは以下の通りです。複合的な経路をたどることもあります。
- メールやSNSの閲覧
- 悪意あるウェブサイトの閲覧
- USBメモリやHDDドライブなどの外部媒体
- 偽装したソフトウェアやアプリ
- 脆弱性の悪用
- ワームやボットなどのネットワーク経由
なかでも一番多い経路は、メールを経由した感染です。
今までは不完全な日本語でのメールが多く、ユーザー本人も不審なメールだと気付くことが多かったですが、昨今はAIにより自然な日本語で送られることがあります。
送信者をよく確認することや、添付ファイルはメール本文に記載されたURLはクリックしない、などの対応をユーザーである従業員一人一人が行う必要があります。
マルウェアの感染経路は多岐にわたり、単一の対策では防げないのが実情です。
IT担当者は、技術的対策・組織的対策・人的対策の3層で防御を重ねる「多層防御(Defense in Depth)」を意識し、組織のセキュリティ強化を図る必要があります。
企業PCがマルウェア感染した際の被害・リスク

企業においてPCやシステムがマルウェア感染した場合、どのような被害が考えられるでしょうか。また、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
影響範囲は幅広いですが、代表的なものを記載します。
1.個人・機密情報の漏洩
まずあげられるのは、個人情報や企業の重要な機密情報の流出です。
重要情報が漏洩した場合、社会的な信用が失墜し、顧客に対し損害賠償が発生したり、行政処分や法的責任が発生したりする場合があります。
2.業務やサービス・サイトの停止
業務システムやサーバーがマルウェアに感染した場合や、ランサムウェアによりファイルが暗号化してしまった場合は、生産ライン・物流・営業活動を一時停止する必要が発生します。
結果、顧客対応やサービス提供の遅延や中断が発生し、代替手段の確保などのコストが発生します。
3.感染拡大(社内・取引先)
影響範囲が、当事者や発生企業だけでなく、取引先などにも及ぶ場合があります。
マルウェアの恐ろしい点は、他者への感染が起こりうるということです。
感染したシステムを踏み台にし、他者に攻撃を加えます。そして自らが加害者になってしまい、法的責任を負うこともあり得ます。
その結果、他社に損害を与え、損害賠償請求される可能性もあり、取引停止や信頼関係が破綻することもあります。
発生した被害による損害賠償などは大きいですが、何よりも甚大な影響は顧客離れなどによる信用の失墜です。信用回復には時間やコストがかかります。
企業におけるマルウェア感染の被害は、「見える被害(業務停止・金銭損失)」と「見えにくい被害(信用・法的リスク)」の両面が存在します。IT担当者は、単なる技術的対策だけでなく、組織的なインシデント対応計画(CSIRT構築・演習)や従業員教育を含めた包括的なリスクマネジメントを行うことが求められます。
情シス担当者が行うべきマルウェア・セキュリティ対策

マルウェア感染を防ぐためには、技術的対策と組織的運用を組み合わせた多層防御が不可欠です。
情シス担当者が行うべきマルウェア対策やセキュリティ対策は何があるでしょうか。
1.ウイルス対策ソフトの導入と定期更新
ウイルスへの対応として第一に挙げられるのはウイルス対策ソフトの導入です。ウイルス対策ソフトを導入し、定期更新を行うことで一定のセキュリティ対策を実施できます。
しかし、マルウェアは日々進化をし続け、ファイルレスマルウェアなどのように検知されず、ウイルス対策ソフトでは対応しきれない場合もあります。
そういったマルウェアに対応するため、機械学習や振る舞い検知の仕組みがある最新型のソリューションを導入することもお勧めです。
2.OSやソフトウェアを常に最新の状態にする
マルウェアの感染経路として多いものは、やはりOSやソフトウェアの脆弱性を悪用したケースがほとんどです。
各種ベンダーは、脆弱性を発見次第、セキュリティパッチを配布します。
セキュリティパッチを適用しないまま使用することは、脆弱性という穴を放置したままということです。結果、その脆弱性を悪用したインターネット上から攻撃されます。
したがって、定期的なパッチの迅速なアップデートは、マルウェアの侵入を防ぐための「第一防衛線」です。
特に企業では、「誰が、どの端末で、どのソフトを、どのタイミングで更新したか」を可視化・統制することが重要です。技術的対策だけでなく、組織的運用の仕組み化が、マルウェア感染のリスクを大幅に低減させます。
3.アクセス制限や管理
また、企業情報の流出を防ぐためには、適切なアクセス制限を行うことも重要な点です。アクセス権の適切な付与は、マルウェア感染時の被害拡大を防ぐ「抑止力」および「被害最小化策」として効果を発揮します。
万が一マルウェアに感染してしまったとしても、そのユーザーの権限で使用できる範囲でしか流出することはなく、内部不正や情報流出を防ぐことができます。
また、特権アカウントを厳格に管理することで、影響範囲を狭めることができます。
マルウェアはシステムだけではなく「人の権限」を通じても広がります。そのためにも、技術的対策だけでなく、組織的な権限設計・運用ルールの整備が不可欠です。
4.従業員への情報セキュリティ教育の徹底
マルウェア対策として特に重要なのは、従業員に対し、適切な情報セキュリティ教育を行うという、組織的運用を適切に実施することです。
マルウェアの多くが、人為的なミスや認識不足を起点として侵入します。したがって、技術的対策と同等かそれ以上に「人のリスク」を管理することが何よりも重要です。
先述の通り、マルウェア感染として一番多い経路はメールによる感染です。
・メールに記載されているURLは不用意に開かない。
・メールに添付されているファイルは不用意に開かない。
最近のメールでの攻撃の場合、文面やドメイン、送信者名も精巧に偽装されています。システムでも対応をしていますが、何よりも重要なのは違和感に気付き、不必要な行動を取らないことです。
また、下記のようなことを行わせないための教育が重要です。
・不審なUSBメモリなどの外部記憶媒体を接続しない。
・不要なソフトウェアをインストールしない。
マルウェアに対するリスクを防ぐためにも、従業員に対するセキュリティ教育は非常に重要です。
企業のIT対策は、どれだけ堅牢なシステムを導入しても、最後は「従業員の行動」によって決まるため、セキュリティ教育はマルウェア対策において不可欠です。
特に、「教育=コスト」ではなく、「教育=最大の投資」と捉えることが何よりも重要です。
まとめ
今回は、企業内IT担当者向けにマルウェア対策として有用なことをまとめました。
システムを用いた攻撃のため、システムを用いた対応は必要不可欠です。
しかし、マルウェアは人を標的としたものが多いため、やはり最終的な防波堤は従業員であるユーザーの意識です。セキュリティに対する意識を持ち、適切な使用をすることが何よりも重要なマルウェア対策となります。
そのためにも、従業員に対し適切なセキュリティ教育を行うことは、何よりも重要なマルウェアへの防御策となることでしょう。